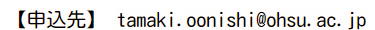■2025年01月13日(日)第16回言語聴覚療法技術セミナー
 「運動負荷の可視化」
「運動負荷の可視化」
発生発語官の運動訓練についてsEMGを用いて客観的に観察する
内容
言語聴覚士が構音訓練や嚥下訓練などの臨床で日々行う発声発語器官の運動訓練は,『過負荷を基本とする』と教科書などで示されています.加えて,『速筋繊維には高負荷を短時間,遅筋繊維には低負荷を長時間実施する』などの記載も散見されます.しかし,実際の臨床では,可視化することがなければ負荷のかけ方は明確になりません.例えば咀嚼訓練はどのようにすると過負荷となるでしょうか.言語聴覚士の多くが行う舌骨上筋群のレジスタンストレーニングは方法が多数開発され報告されていますが,それぞれの方法がどの程度の筋活動であるかは,まだ十分示されているとは言えません.現状においては,患者様本人が実施しやすい方法や言語聴覚士が提供しやすい方法で行われているのが実情であると思われます.臨床推論を明確にして実施される現代のリハビリテーションにおいては,更なる情報が必要かもしれません.
加えて,私たち専門職が提供するリハビリテーションは,科学的理論に基づき客観的にその効果を確認しながら行われることが求められます.それが,確実な訓練成果に繋がり,コミュニケーション活動や食べる活動やその支援へとつながるはずだからです.患者様自身もそれを望まれているはずです.
今回は,前回の技術セミナーで好評頂いた「表面筋電計」を用いて,発声発語器官や嚥下関連器官の運動訓練の負荷に焦点を当ててその可視化も含めて皆さまと一緒に学びたいと思います.表面筋電計は,筋電計測や分析によって様々な筋活動情報が得られますが,今回はモニタリングとして用いて,参加者の皆さまが臨床活動で行っておられる運動負荷と実際の筋活動との関係を観察しご覧頂く予定にしています.
お申込みフォーム

※まれにメール送受信の不具合がみられますので、1週間程度経過してもメールが届かない場合は、
お問合せフォーム または 下記までご連絡ください。
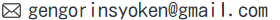
申込受付完了後の予定
・Zoom の URL等 の情報をメールで送らせていただきます。
※参加費の入金が確認できた方のみに送らせていただきます。
お支払済みにも関わらず Zoom情報が届かない場合は、
下記のメールアドレスまたはホームページのお問合せフォームからご連絡ください。
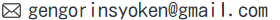
・講義資料は、セミナー当日までに本ホームページに掲載します。
ダウンロードするためのパスワードをメールでご連絡しますので、各自ダウンロードしてご利用ください。
お支払方法
下記のいずれかでお願いいたします。
<クレジットカード決済の場合>
申し込み受付時の返信メールで決済用URLをお知らせします。
URLにアクセスし、お手続きください。
<銀行振込の場合>
下記の講座にお振込みください。
三菱UFJ銀行 上本町支店
口座番号:普通 0226125
口座名義:言語聴覚療法臨床研究会
※振込手数料は各自ご負担ください。
「嚥下訓練中の筋活動を可視化しその特徴を知ろう」
「言語聴覚士が行う摂食訓練~食物を用いたリハビリテーション実施のポイント~」
「安心安全な嚥下訓練の提供 フィードフォワード的臨床思考とその実践」
「Articulation訓練時の視点と実際:嚥下訓練との相違点」
「嚥下訓練ですべきこと 曖昧にしてはいけないこと
-摂食嚥下リハビリテーション手技の基本を振り返る-」
「復唱からの発見 -言語症状の読み解き方-」
「言語聴覚療法におけるバイオフィードバック訓練 -正確で効果的な運動訓練を目指して-」
「摂食嚥下訓練手技の理解と実践 - 運動学的アプローチと効果的な方法 -」
「嚥下造影検査を行う前に言語聴覚士として実施しておく観察や評価 -嚥下動態理解の仮説立案に向けた視点と実際-」
「摂食嚥下障害と頸部聴診 -何を聴き何を得るか-」
「言語聴覚療法での運動負荷の考え方-発声発語訓練・摂食嚥下訓練を中心に-」
「言語聴覚療法におけるバイオフィードバック訓練 ―生体運動の可視化とその活用-」
「摂食嚥下訓練における姿勢調整-何を求めどう調整するか-」
「摂食嚥下訓練における姿勢調整-何を求めどう調整するか-」
「摂食嚥下訓練のスキルアップ - 嚥下表面筋電バイオフィードバック訓練を知る - 」
「摂食嚥下訓練の実際~自身の嚥下訓練手技を運動学的視点から検証しよう~」
「摂食嚥下訓練のUp-to-date~各種訓練法の適応からsEMG バイオフィードバック訓練の実践まで~」
 ~すべての方に最高のサービスを~
~すべての方に最高のサービスを~